地域未来創生スクール 実施状況
「地域未来創生スクール」は地域づくりを担う地方自治体職員等を対象として、地域の未来を担う実践力を備えた人材を育成することを目的としております。
当スクールでは、地域課題に即した対応力を身に付ける「実践型講義」と「プロセスデザイン研修」を実施するとともに、一流講師陣との人的ネットワーク形成の場を提供いたします。
このページでは、令和7年度に開講した当スクールの様子をご紹介します。
(1)第1回日程【令和7年6月4日(水)、5日(木)】
(2)第2回日程【令和7年7月31日(木)、8月1日(金)】
(3)第3回日程【令和7年9月〜10月】
(4)第4回日程【令和7年11月20日(木)、21日(金)】
(5) 受講生の声
(1)第1回日程【令和7年6月4日(水)、5日(木)】
全国の自治体から27人のやる気あふれる受講生が集い、第1回地域未来創生スクールの開講式が行われました。
末宗理事長の挨拶後に、受講生一人ひとりが自己紹介を行い、それぞれの自治体の取組みや、スクールへの意気込みを語りました。会場は終始和やかな雰囲気に包まれ、活気あるスタートとなりました。
続く講義では、質疑応答の時間に多くの質問が寄せられ、受講生が各自治体で直面している課題について具体的なアドバイスを受ける姿もあり、参加者にとって非常に学びの深い時間となりました。

(講義の様子)
また初日の夜には交流会も開催され、全国から集まった受講生同士はもちろん、講義を担当いただいた講師の皆様とも、和やかな意見交換が行われました。地域や立場を超えた対話の中から、新たな気付きやつながりが生まれる、貴重なひとときとなりました。
(交流会の様子)
(2)第2回日程【令和7年7月31日(木)、8月1日(金)】
当スクールの目玉である「プロセスデザイン研修」がいよいよスタートしました。
今回は、まち・ひと・しごとの各テーマごとに、実務家講師が取り組んできた事例を説明し、討論者が深堀りをしていく、事例分析講義を行いました。

(テーマ「ひと」の講義)
講義の中では、事業成功のポイントや困難に直面した際の解決方策などにも触れ、事業のノウハウや地域課題の具体的な解決方法を学んでいきました。
また講義中にも受講生の意見や思いを発表する場面も見られ、受講生参加型でプロセスを深く学ぶ時間となりました。

(テーマ「まち」の講義)

(テーマ「しごと」の講義)
2日目の朝は、各チームごとに最終発表に向けたグループワークを実施しました。
発表内容を踏まえて、現地視察時に確認したいポイントを共有するなど、受講生同士で積極的な意見交換が行われました。

(グループワークの様子)
また受講生同士も和やかになってきて、グループワークだけでなく、講義中も1回目の講義よりもより積極的な質問や意見交換など、熱心な姿勢が随所に見られました。
(3)第3回日程【令和7年9月〜10月】
第3回は、各テーマ「まち」「ひと」「しごと」に分かれ、実務家講師の活動現場を訪問する現地視察を実施しました。
受講生は、講師が実際に地域課題と向き合ってきた現場を歩きながら、地域住民や事業者、行政担当者など、第一線で挑戦を続けるプレイヤーの声に直接触れました。
現地では、各地の取組を単に「成功事例」として見るのではなく、試行錯誤の過程や、地域の人々との信頼関係づくり、そして持続可能な仕組みづくりの裏側まで学びを深めました。
講師と参加者の対話も活発に行われ、教室の中だけでは得られない「現場の温度」を体感する時間となりました。
【まち班:宮崎県日南市】
テーマ「応援の連鎖がまちを変える~油津商店街にみる新しい地方創生のかたち~」のもと、木藤亮太氏(株式会社ホーホゥ)の案内で日南市を訪問しました。

当日は、油津商店街の事業者を中心に、子育て支援センター「ことこと」や「二代目湯浅豆腐店」、IT企業「PORT株式会社」など、多様な取組を視察しました。
商店街の中心に、様々な関係者が協働しながら「人が集う仕組み」を育てており、新たな挑戦が生まれていくまちづくりの現場を学びました。

また飫肥城下町では、歴史的建物を活かした観光まちづくりの取組も見学し、地域資源の新たな活用方法を学びました。

【ひと班:島根県】
テーマ「関係人口創出・移住~私たちはローカルで幸せを見つける~」のもと、指出一正氏(株式会社ソトコト)の案内で、島根県の松江市・出雲市・雲南市・奥出雲町の4地域を訪問しました。

行政の取組「しまっち!」や「しまことアカデミー」に加え、移住者・Uターン者が地域で挑戦する姿を現場で学びました。
空き店舗を活用したコミュニティスペースやカフェ、農業体験を通じた関係人口づくりなど、地域に根ざした多様な実践を視察しました。

また、各地域プレイヤーの移住を決意した背景などを伺うことで、関係人口創出の要因を考えるきっかけになりました。

【しごと班:山形県庄内町】
テーマ「地域資源活用によるビジネス創出~いなかビジネス教えちゃる~」のもと、畦地履正氏(株式会社四万十ドラマ)の案内で、庄内町を訪問しました。

町の特産米である「亀の尾」を軸に、農家・加工業者・販売業者・行政が一体となり進めている「かめこめプロジェクト」を中心に、地域資源を活かした取組を学びました。

「さくら糀屋」の事業承継や新ブランドづくり、「吉祥ファーム」の多品種栽培と販路拡大、「熊谷神社」や「亀の尾の里資料館」での文化継承など、地域に根ざした多様な挑戦を視察しました。
全ての関係者がお互い寄り添いながら進める姿勢や、「あるものを磨き、真ん中をつくる」発想が印象的でした。

(4)第4回日程【令和7年11月20日(木)、21日(金)】
第4回日程は、これまで学んできた「実践型講義」や「プロセスデザイン研修」の集大成となる2日間であり、受講生一人ひとりの探究と挑戦の歩みが鮮明に表れた時間となりました。
2日目は、約半年にわたり取り組んできたプロセスデザイン研修の総まとめとして、「まち」「ひと」「しごと」のテーマごとにチーム発表を行いました。
各チームは、事例分析講義で得た視点や現地視察で掴んだリアルな学び、チーム内で重ねてきた議論を踏まえ、それぞれ実務家講師から与えられた課題に対して提案をまとめました。
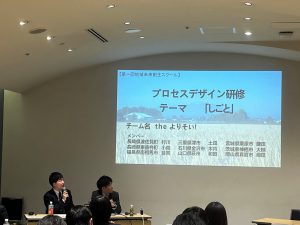

どの発表も、現場での学びが深く反映された非常に高いクオリティで、実務家講師・討論者からも「深い仕上がりになっている」「視察先の自治体にも伝えたい」と高い評価が寄せられました。
また、受講生一人ひとりがこのスクールで得た学びや、今後どのように活かしていきたいかを語るなど、最終回にふさわしい、希望に満ちた時間となりました。

全ての講義・研修を終え、最後に閉講式が行われました。
はじめに末宗理事長より、半年間の受講生の成長と挑戦に対する激励の言葉が述べられ、続いて講師代表として小田切徳美先生(明治大学 農学部 教授)から、受講生の今後の実践につながる期待が語られました。
その後、受講生一人ひとりに修了証と記念品が授与され、会場には達成感と晴れやかな雰囲気が満ちていました。

その後の交流会では、講師と受講生、受講生同士がテーブルを囲みながら、最終発表を振り返ったり、各地域での課題や挑戦について語り合う姿があちこちで見られました。
また世代や地域を超えて本音で語り合う時間となり、「ここからまた一緒に頑張ろう」と励まし合う声も聞こえるなど、スクールを通じて育まれたネットワークの強さを実感できるひとときとなりました。


(5) 受講生の声
4回の日程を終えた受講生からは、「地域を見る視点が大きく変わった」「行政として何をすべきかを丁寧に考える重要性を実感した」といった声が多く寄せられました。
現場での対話の大切さ、数字だけでは測れない価値、地域資源の磨き上げなど、実務に直結する学びが得られたとの意見も多く見られました。
また、全国から集まった受講生同士の交流についても、「他自治体の熱量に刺激を受けた」「自分にはない発想や行動力に触れた」「悩みを共有できる仲間の存在が心強かった」といった声が多く聞かれ、スクールを通じて形成されたネットワークへの評価が非常に高いものとなりました。
受講生がスクールで得た学びを活かして、それぞれの地域で新たな挑戦を生み出し、地域の未来をつくる原動力となることを期待しています。




