地域未来創生スクール 第2期生募集
「地域未来創生スクール」は地域づくりの最前線に立つ自治体職員や関係者を対象に、
地域課題に即した実践的な知識とスキルを体系的に身につけることを目的としています。
当スクールでは、地域づくりに高い知見をもつ学識者や経験豊富な実務家等の講師陣から地域課題に対するアプローチ手法を学び、地域課題に即した対応力を身につける「実践型講義」と「プロセスデザイン研修」を行っていきます。
また、第一線で活躍する専門家や全国から集まる受講生との交流を通じて、スクール終了後も続く人的ネットワークを形成できることも大きな特徴です。
1 募集概要
(1)募集期間
令和7年11月10日(月)~令和8年1月30日(金)
(2)募集人数
30名程度
(3)申込方法
連絡担当者より、以下の 参加申込書(様式第1号)及び 経歴書(様式第2号)を地域総合整備財団〈ふるさと財団〉 地域再生部事業推進室へメール又は郵送にて提出してください。
(4)各種様式
参加申込書(様式第1号)
経歴書 (様式第2号)
※詳細は、募集要項をご確認ください。
2 講座概要
(1)実践型講義担当講師紹介

島の現状は日本の未来であると同時に、島にこそ日本の未来を創るヒントがあると考えます。戦後70年間で人口が3分の1に減少し、財政再建団体への転落予測を受けた海士町が、生き残りをかけて挑んできた改革と戦略から、これからのまちづくりに必要なことを考えます。

「地域づくり」とは、地域の新しい仕組みを「つくる」ことを意味しています。 現代に即して言えば、「人口が減少しても、地域で幸せに住み続けること」を住民の力、関係人口等の外部の力、自治体の力を糾合して推し進めることです。 その体系と具体策を論じます。

 観光による地域の活性化・再生を進める際、地域を上手くマネジメントする「観光 まちづくり」という考え方が重要となります。その要諦は①状況把握、②戦略策定、③魅力創出、④滞在化・平準化、⑤保存・活用、⑥組織・人材、⑦ブランド形成、 ⑧財源確保、⑨危機管理などですが、中でも地域の将来「ビジョン」、それを実現 させる「組織」、そして組織を維持し、ビジョンを実現するのための「財源」の3つについて分かり易く解説します。
観光による地域の活性化・再生を進める際、地域を上手くマネジメントする「観光 まちづくり」という考え方が重要となります。その要諦は①状況把握、②戦略策定、③魅力創出、④滞在化・平準化、⑤保存・活用、⑥組織・人材、⑦ブランド形成、 ⑧財源確保、⑨危機管理などですが、中でも地域の将来「ビジョン」、それを実現 させる「組織」、そして組織を維持し、ビジョンを実現するのための「財源」の3つについて分かり易く解説します。
講 師:金丸 弘美 (食環境ジャーナリスト・食総合プロデューサー)

農産物のブランド化には食のテキスト化と参加型の食のワークショップが 大きな力になります。食材の品種、栽培歴、栄養価、食べ方までを提案するものです。商取引や子どもたちの教育や体験農業などで、具体的に語ることができるようになり訴求力も高まる地域ブランディングの仕組みを、事例をもとに説明します。

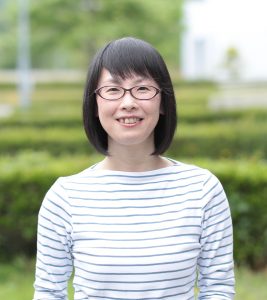



 地域の持続可能戦略は大きな課題です。本講義では 「グローバルな環境
地域の持続可能戦略は大きな課題です。本講義では 「グローバルな環境
変化と地域」という文脈から地域における脱炭素とネイチャーポジティブ
の意義について解説します。さらに、それらをまちづくりにつなげていく
ための方法論を現在の課題と共に考えます。
 今、地域は、人口減少等様々な課題を抱えており、全てに行政が対応できる
今、地域は、人口減少等様々な課題を抱えており、全てに行政が対応できる
(2)プロセスデザイン研修担当講師紹介
テーマ:【しごと】地域資源活用によるビジネス創出~いなかビジネス教えちゃる~
実務家講師:畦地 履正 (株式会社四万十ドラマ 代表取締役)
 いなかでも「こんなことをしてる・こんなことができる」という希望に対する答えは現場にあります。あしもとにあるものをもう一度見直すことによって宝物が生まれた瞬間を、皆さんと一緒に体感していきます。そして今度は「皆さんの宝物」を一緒に探しにいきましょう。
いなかでも「こんなことをしてる・こんなことができる」という希望に対する答えは現場にあります。あしもとにあるものをもう一度見直すことによって宝物が生まれた瞬間を、皆さんと一緒に体感していきます。そして今度は「皆さんの宝物」を一緒に探しにいきましょう。
討論者:図司 直也 (法政大学 現代福祉学部 教授)
 四万十での経験を起点にして、各地の現場に赴き、ひとと資源を活用しながら、ビジネス創出に導く畦地講師の実践プロセスに学びます。
四万十での経験を起点にして、各地の現場に赴き、ひとと資源を活用しながら、ビジネス創出に導く畦地講師の実践プロセスに学びます。
その要点は何か、受講生の皆さんの足元を見つめ直すヒントを一緒に探りましょう。
テーマ:【ひと】関係人口創出・移住~私たちはローカルで幸せを見つける~
実務家講師:指出 一正 (株式会社ソトコト 代表取締役 ソトコト編集長)
 「観光以上、移住未満の第三の人口」と称される関係人口。各地で人口減少・高齢化が進むなか、地域づくりの担い手としての存在に期待が集まっています。関係人口とは何か? 関係人口が生まれることによる地域の変化は? どう関係人口や移住者を呼び込むかなど、2012年にスタートした島根県の関係人口講座「しまコトアカデミー」をはじめ、全国の関係人口創出と移住促進の好例をもとに、実態と背景、傾向をわかりやすく解説していきます。
「観光以上、移住未満の第三の人口」と称される関係人口。各地で人口減少・高齢化が進むなか、地域づくりの担い手としての存在に期待が集まっています。関係人口とは何か? 関係人口が生まれることによる地域の変化は? どう関係人口や移住者を呼び込むかなど、2012年にスタートした島根県の関係人口講座「しまコトアカデミー」をはじめ、全国の関係人口創出と移住促進の好例をもとに、実態と背景、傾向をわかりやすく解説していきます。
討論者:小田切 徳美 (明治大学 農学部 教授)
 関係人口は、わかりやすくかつ奥深い存在です。だれでも関係人口が地域に必要であることはわかりますが、なぜそうなのかはなかなか説明できません。関係人口を世の中にはじめて提唱した実践家講師とともに、「なぜ」、「どうしたら」を徹底的に掘り下げます。
関係人口は、わかりやすくかつ奥深い存在です。だれでも関係人口が地域に必要であることはわかりますが、なぜそうなのかはなかなか説明できません。関係人口を世の中にはじめて提唱した実践家講師とともに、「なぜ」、「どうしたら」を徹底的に掘り下げます。
テーマ:【まち】応援の連鎖がまちを変える~日南市・油津商店街にみる地方創生のかたち~
実務家講師:木藤 亮太 (株式会社油津応援団 取締役)

油津商店街(宮崎県日南市)の再生事業の話題を中心に、地方創生、まちづくり、地域活性化について分析し、人口減少の中でどのような手法が有効なのかを紐解きます。
再生しない”再生事業”がはじまって12年。行政事業が先導した4年、民間の力で自走しはじめた4年、そしてコロナ禍を乗り越え新たなステージを目指した4年。それぞれのプロセスはどうデザインされ、実践され、変化に適応していったのかについて意見交換します。
討論者:根岸 裕孝 (宮崎大学 地域資源創成学部長 教授)
 実務家講師は「まちなか再生請負人」として、衰退の一途であった日南市油津商店街を見事に蘇らせました。家族で地域に飛び込み、多くの人を繋ぎ、夢をカタチにするチカラとは どのようなものなのかを体現したプロセスについてやりとりを通じてより具体的に引き出していきます。
実務家講師は「まちなか再生請負人」として、衰退の一途であった日南市油津商店街を見事に蘇らせました。家族で地域に飛び込み、多くの人を繋ぎ、夢をカタチにするチカラとは どのようなものなのかを体現したプロセスについてやりとりを通じてより具体的に引き出していきます。
テーマ:【まち】自治体毎の空き家対策を考える~実践の中から見つける、あなたのまちの空き家対策~
実務家講師:有江 正太 (NPO法人空き家コンシェルジュ 代表)

空き家問題は、地域毎に課題や有効な対策は大きく異なります。地域課題に即した空き家総合相談窓口構築やプラットホーム構築、自治体組織再編等、自治体毎の支援を専門団体として実施しております。その事例を基に他地域に活かせる空き家対策を共に考えます。
討論者:野澤 千絵 (明治大学 政治経済学部 教授)
 空き家対策は、地域特性・担い手の状況等でアプローチが全く異なります。これまで数多く空き家対策の実践経験を有する講師との討論を通じて、受講生の皆様が自らのまちに合った空き家対策を見出し、実践への第一歩を踏み出す機会にして下さい。
空き家対策は、地域特性・担い手の状況等でアプローチが全く異なります。これまで数多く空き家対策の実践経験を有する講師との討論を通じて、受講生の皆様が自らのまちに合った空き家対策を見出し、実践への第一歩を踏み出す機会にして下さい。

